生涯独身の「おひとりさま」が増えています。親族が誰もいない、もしくは疎遠になっている場合、自分が亡くなったあとの財産はどうなるのでしょうか。相続問題に詳しい田中伸顕弁護士に、おひとりさまが相続に向けてやっておくと良いことを聞きました。

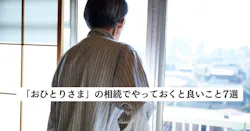
相続する際、遺産を独り占めしたいと企む相続人も中にはいるでしょう。「遺産をすべて相続したい」と主張したり、遺産を隠したり使い込んだりするような場合です。また、「一人の相続人に全財産を譲る」という遺言が残されているケースもあります。このような場合でも、他の相続人には自身の相続分を主張する権利があります。この記事では、遺産の独り占めへの対処法を詳しく解説します。


被相続人の生前に、介護や家業の手伝いなどの援助をしていた場合、相続する際に相続の取り分を増やしてほしいと考える相続人もいるでしょう。このようなケースでは、「寄与分」という形で相続分の増額を主張できる可能性があります。 寄与分が認められるのはどのような場合なのか、どの程度の増額が見込まれるのか、といった点について詳しく解説します。


遺言書を作成しても、相続人に発見されなかったり、改ざんされたりしてしまっては意味がありません。そこで、自分で作成した遺言書を法務局に保管できる制度が2020年から始まりました。この記事では、自筆証書遺言書保管制度の内容やメリット、注意点などについて詳しく解説します。

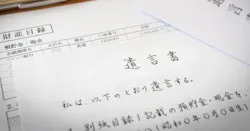
内縁や事実婚のパートナーに相続権はありませんが、遺産を残す方法はあります。この記事では、内縁や事実婚のパートナーに遺産を残すために生前にできる対策を詳しく解説します。


親族が亡くなり相続の手続きを進めている最中に、相続人代表者指定届が役所から届くことがあります。この記事では、相続人代表者指定届の内容や書き方、代表者になった相続人の役割、無視した場合の罰則などについて詳しく解説します。


相続関係説明図は、不動産の相続登記手続きをする際に予め用意しておくと便利な書類です。この記事では、相続関係説明図の用途や作成方法、法定相続情報一覧図との違いを詳しく解説します。

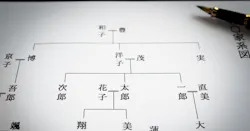
相続手続きの費用は、自分で行う場合と専門家に依頼する場合とで大きく異なります。また、専門家の中でも、弁護士や司法書士、税理士、行政書士の誰に依頼するかによって費用は異なります。この記事では、相続手続きにかかる費用を詳しく解説します。


養子縁組は、相続税対策の方法として用いられることがあります。たしかに養子縁組は相続税対策として有効な場合がありますが、トラブルのリスクにも注意しなければなりません。弁護士などのサポートを受けながら、効果的に相続対策を行いましょう。この記事では養子が相続人になる場合について、相続割合・相続税の取り扱いや注意点などを解説します。


遺産相続の手続きは多岐にわたります。中には期限がある手続きもありますので、スケジュールを立てて、早い段階から計画的に相続手続きを進めましょう。この記事では遺産相続の手続きについて、流れや方法、期限などを解説します。


弁護士には、相続に関する対応全般を依頼できます。トラブルなくスムーズに相続手続きを終えたい方や、他の相続人と揉めてしまっている方は、弁護士に相続手続きを依頼しましょう。この記事では、相続手続きを弁護士に依頼するメリット、弁護士費用、弁護士と税理士・司法書士の違いなどを解説します。


兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には「遺留分」が認められています。相続などによって取得した財産が遺留分額を下回った場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。遺留分額を計算するためには、遺留分割合を確認する必要があります。この記事では、遺留分の計算例やケース別シミュレーションを紹介します。

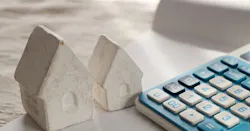
相続登記は、一般的には司法書士に依頼しますが、法務局または地方法務局にて自分で手続きを行うことも可能です。相続登記の手続きを自分で行うと、不動産1件当たり5万円から15万円程度の司法書士費用を節約できます。この記事では、相続登記の手続きを自分で行う際の基礎知識として、手続きの流れや必要書類、費用などを解説します。


不動産を相続した場合は、その所在地の法務局または地方法務局で相続登記の手続きを行う必要があります。相続登記するには、公的書類の取得費用や登録免許税、専門家に依頼した場合の報酬などの費用がかかります。この記事では、相続登記にかかる費用の詳細や費用を抑える方法について解説します。


不動産を相続した際には、遺産分割や相続登記などの手続きが必要になります。弁護士のサポートを受けながら、スムーズに不動産の相続手続きを進めましょう。この記事では不動産の相続について、手続きの流れ・分割方法・評価方法・費用・必要書類などを解説します。

