親が借金を抱えたまま亡くなった場合、相続放棄することで借金の返済義務を回避できます。この記事では、相続放棄ができないケースや注意点、相続放棄した場合に借金を誰が払うのかについても詳しく解説します。


相続放棄の手続きは、相続人が単独で行うこともできますが、兄弟姉妹など同じ相続順位であれば、複数の相続人がまとめて行うこともできます。この記事では、兄弟姉妹でをまとめて相続放棄できるのか、その場合の必要書類などについて詳しく解説します。
.jpeg?w=115)
.jpeg?w=250)
配偶者や子どもだけでなく、孫にも自分の財産を与えたいと考える方はたくさんいらっしゃいます。孫は法定相続人でないため、財産を与えるためにはなんらかの対策が必要です。弁護士のアドバイスを受けながら、家庭の状況に合わせた対策を検討しましょう。 この記事では、孫に遺産を相続させる方法、相続以外で孫に財産を渡す方法、孫に財産を渡す際の注意点などを解説します。


本人が亡くなったことを機に財産を譲り渡す方法としては、相続・遺贈(遺言書)のほかに「死因贈与」があります。死因贈与を行うに当たっては、生前の段階で死因贈与契約書を締結しておきましょう。また、死因贈与には相続税がかかることがある点にも注意が必要です。この記事では死因贈与について、遺贈との違い、贈与契約書のひな形、税金(相続税)の取り扱いなどを解説します。


各金融機関は、遺言書の作成をサポートする「遺言信託」を受け付けています。遺言信託は一見便利なようですが、専門家への依頼が別途必要になるなど、ワンストップでのサポートとはいかないケースも多いです。サービス内容や手数料などを確認した上で、本当に遺言信託を利用すべきかどうかよく検討しましょう。 この記事では遺言信託について、仕組み・メリットとデメリット・費用・手続き・トラブルなどを解説します。


遺言書を作成する際には、信頼できる人を遺言執行者に指定するのが安心です。遺言執行者を指定すれば、ご自身の死後、遺言書の内容を実現するための業務を行ってもらえます。この記事では遺言執行者について、役割・権限・選任方法・業務内容・選任のメリットなどを解説します。


遺言書を作成する方法としては、「自筆証書遺言」がもっともお手軽です。自分で自筆証書遺言を作成する方もたくさんいらっしゃいますが、書式・遺言能力に関するルールや、偽造・変造・紛失のリスクに注意しなければなりません。自筆証書遺言書保管制度の活用を含めて、自筆証書遺言が無効にならないように注意深く作成しましょう。この記事では自筆証書遺言書の書き方について、自分で作成する際の例文や手続きなどを解説します。


遠方にあるなど管理が難しい土地を相続した場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。不要な相続土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。この記事では相続土地国庫帰属制度について、利用要件・手続きの流れ・費用などを解説します。


「遺産分割協議証明書」とは、各相続人が遺産分割協議の内容を証明する書類です。相続人が遠方にいたり連絡が取りづらかったりする場合に、遺産分割協議書の代わりに作成することができます。この記事では遺産分割協議書との違いや遺産分割協議証明書のメリットとデメリット、遺産分割協議証明書の書式について詳しく解説します。


遺産分割協議書とは、遺産分割に関する話し合い(遺産分割協議)で合意した内容をまとめた書面です。遺産分割協議書を作成する際には、戸籍謄本など必要書類がたくさんあります。この記事では、遺産分割協議書の必要書類や取得方法、有効期限について詳しく解説します。

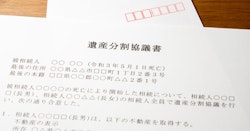
成年後見に関する登記事項証明書は、成年後見人が本人を代理して法律行為をする場合や、本人がした法律行為を取り消す場合などに必要です。 この記事では成年後見に関する登記事項証明書の請求方法や必要書類、有効期限などを解説します。


遺産分割協議書は、相続手続きの内容に応じて、銀行、法務局、証券会社、税務署、運輸局、市区町村役場などに提出します。手続きによっては提出期限がある場合もあるので、計画的に進めましょう。この記事では、遺産分割協議書の提出先や期限、コピーの可否などについて詳しく解説します。


遺産分割協議書の作成後に不備に気づいたり騙されて合意したりした場合には、遺産分割協議書の無効や取り消しを主張できる可能性があります。この記事では、遺産分割協議書の無効や取り消しを主張できるケースや手続きについて詳しく解説します。


相続放棄をすれば亡くなった人の借金を相続せずに済み、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。ただし、相続放棄が家庭裁判所に受理されず、却下されてしまう場合もあるので注意が必要です。この記事では、相続放棄ができない・認められないケースや、相続放棄を失敗しないための注意点などを解説します。

