
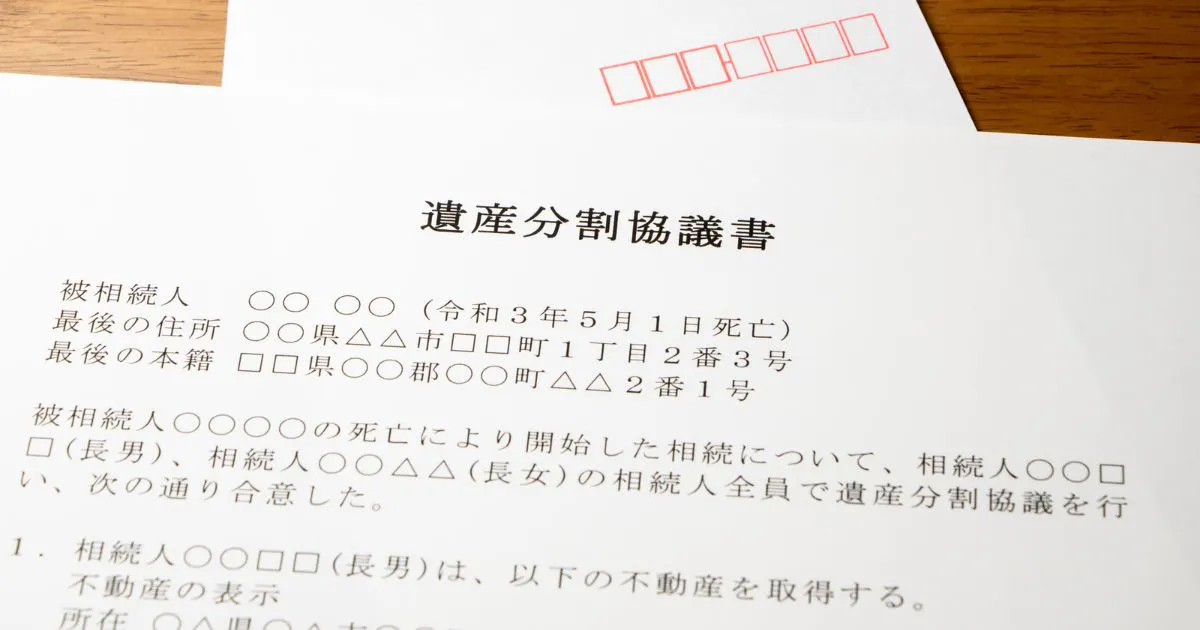
遺産分割協議書を作成する際には、次のような書類が必要です。
被相続人の戸籍謄本は、遺産分割協議を行う前提として、相続が開始したことを証明し、相続人を正確に特定するために必要です。
遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員が協議に参加する必要があります。そのため、相続人を正確に特定することが重要です。また、遺産分割協議書を作成した後の相続手続きでも被相続人の戸籍謄本の提出が求められます。
取得が必要な戸籍謄本の範囲は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本です。
戸籍謄本を取得する方法は2つあります。1つ目は被相続人の本籍地の市区町村役場へ申請する方法です。
窓口へ行くか、郵送で申請できます。被相続人が結婚と離婚を繰り返していたり、転居をしたりなどで本籍地の変更が何度もある場合には、以前の本籍地のある市区町村役場にも戸籍謄本の取得を申請しなければなりません。
こうした戸籍取得の時間や手間を短縮するため、2つ目の方法として、2024年3月1日から、全国どこの市区町村役場でも一括してすべての戸籍謄本を取得できるようになりました(広域交付)。
取得したい戸籍謄本が複数の市区町村役場に存在する場合でも、一つの市区町村役場でまとめて申請できます。
ただし、郵送はできず、代理申請もできないため、本人が窓口に行く必要があります。また、戸籍の附票は広域交付の制度は利用できません。自身の取得したい戸籍謄本が広域交付で取得できるか気になる場合は、詳しくは最寄りの市区町村役場に問い合わせましょう。
被相続人の戸籍謄本と同じく、相続人の正確な特定のために使用します。また、遺産分割協議書を作成した後の相続手続きでも相続人の戸籍謄本の提出が求められます。
取得が必要な戸籍謄本は、相続人の現在の戸籍謄本です。それぞれの本籍地の市区町村役所へ申請します。
遺産に不動産が含まれる場合で、不動産の登記簿上の住所と被相続人の戸籍上の本籍地が異なる場合には、被相続人の住民票または住民票除票、戸籍附票が必要です。
住民票には、被相続人の最後の住所が記載されています。住民票除票には、住民票に記載された住所の1つ前の住所が記載されています。住民票の除票で2つ前の住所を証明したい場合には、1つ前の住所地の市区町村の住民票除票を取得します。
戸籍附票には、その戸籍内に入っている期間の住所の履歴が記載されています。
これらの書類と登記簿を照らし合わせることで、登記簿上の所有者と被相続人が同じ人物であることを証明します。
住民票や住民票の附票は被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得できます。戸籍の附票は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
遺産分割協議書には、署名とともに実印を押印することが一般的です。実際に使われた印鑑が実印であることを証明するために、相続人の印鑑登録証明書を遺産分割協議書に添付します。
また、遺産分割協議書を作成した後の相続手続きでも相続人の印鑑登録証明書の提出が求められます。
印鑑登録証明書は、住民登録がある市区町村で請求できます。印鑑登録をしていない場合には、実印を登録する手続きが必要です。
遺産分割協議書を作成する際には、財産目録が必要です。財産目録とは、相続の対象となる全ての財産について、種類や内訳、評価額などを一覧にまとめたものです。
財産目録は、遺産分割協議を進める上で、相続財産を正確に把握し、遺産分割協議をスムーズに進めるために必要です。また、相続税の計算にも必要な情報となります。
財産目録は、相続人が協力して作成します。
財産目録を作成するために、以下のような書類を用意するとよいでしょう。
遺産分割協議書を作成する際には、遺言書の有無を確認することが必要です。
遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って遺産を分けるので、遺産分割の必要はありません。遺言書に記載されていない遺産がある場合や、遺言書がない場合には、遺産分割協議で遺産の分け方を話し合う必要があります。
そのため、遺産分割協議を始める前に、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書には、以下の3つの種類があります。
まず、自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を書き、日付と署名・押印した遺言です。自筆証書遺言は自宅や貸金庫など、被相続人が保管した場所にあります。また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合には、法務局で確認できます。
次に、公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもと、遺言者の遺言内容を記録し、公正証書として作成した遺言です。公証役場で遺言を検索できます。
最後に、秘密証書遺言は、遺言者が自筆または第三者によって書かれた遺言書に署名・押印し、封印した後に、公証人と証人の前で自己の遺言である旨などを申述し、公証人と証人の署名押印のある封紙が作成された遺言です。秘密証書遺言は遺言者が保管しているので、自宅や貸金庫などで見つかる可能性があります。
遺言書が見つかった場合、その遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言の場合には、検認済み証明書が必要です。検認とは、家庭裁判所で相続人立ち会いのもとに遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認済み証明書は、家庭裁判所の検認の手続きの際に申請できます。
なお、自筆証書遺言の場合でも、法務局で保管されていたものについては検認は不要です。
相続人の中に相続放棄をした者がいる場合には、相続放棄受理証明書が必要です。
相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったと扱われ、その結果、次の順位の相続人がいる場合にはその人が相続人になります。遺産分割協議が有効に成立するためには、相続人全員が協議に参加する必要があるため、相続人を正確に特定するために、相続放棄受理証明書が必要になります。
他の相続人が相続放棄をしているかどうかわからない場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述の有無を照会できます。
遺産分割協議で寄与分や特別受益を主張する場合には、寄与分や特別受益を証明する書類が必要です。
寄与分とは、被相続人の生前に相続人の一部が被相続人の財産の増加や維持に貢献した分のことです。例えば、被相続人の介護を長期間に渡り続けていたり、企業の経営に寄与した場合などが考えられます。寄与分が認められると、その相続人は法定相続分に上乗せして、相続財産を受け取ることができます。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与によって特別に受けた利益のことです。もし特別受益がなければ、本来の相続財産はもっとあったと考えられます。そのため、特別受益がある場合には、特別受益の額を遺産の額に足して、各相続人の相続分を計算します。特別受益を受けた相続人は、その額から特別受益を差し引いた分のみを相続します。
寄与分や特別受益を考慮することにより、より公平で適正な相続額を算定できるようになります。
寄与分の場合には介護をしていたことを証明する書類や、会社の経営に貢献したことを証明する書類など、特別受益の場合には遺贈や生前贈与を証明する書類などを用意しましょう。
遺産分割協議書に有効期限はありません。何年前の遺産分割協議書でも、相続手続きに使用できます。
ただし、相続手続きには期限があるものがあります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。また、2024年4月1日以降は相続登記にも3年以内の期限が設けられます。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるので、相続手続きは早めに済ませるようにしましょう。
遺産分割協議書の作成に必要な書類に有効期限はありません。
ただし、相続人の戸籍謄本と印鑑登録証明書については、時間が経つと内容が変更される可能性があることから、金融機関などでは、「発行から6か月以内」「発行から1年以内」といった有効期限が設定されていることがあります。
相続登記をするために法務局で必要な書類は、次のとおりです。
預貯金の払い戻しや名義変更をするために必要な主な書類は以下のとおりです。金融機関によってはこれらの他にも書類の提出が求められる可能性があります。手続きを行う金融機関に確認しましょう。
証券会社で株式や投資信託などの有価証券の名義変更をするのに主な必要書類は以下のとおりです。証券会社によってはこれらの他にも書類の提出が求められる可能性があります。手続きを行う証券会社に確認しましょう。
普通自動車の名義変更に必要な書類は、次のとおりです。
ただし、遺産である自動車が普通自動車で、査定額が100万円以下の場合には、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」と、査定額が100万円以下であることを証明できる資料を提出することで、遺産分割協議書を省略できます。
軽自動車の名義変更に必要な書類は、次のとおりです。
相続税の申告に必要な書類は、次のとおりです(遺産の内容によっては、追加で書類が必要になる可能性があります)。
遺産分割協議書の作成には、相続人や遺産の範囲を確認するために様々な書類が必要です。また、相続手続きで遺産分割協議書を提出する際には他の書類も必要となるので注意が必要です。遺産分割協議書の作成や相続手続きを負担に感じる場合には弁護士に依頼することもできます。遺産分割協議書の書類集めには時間や手間がかかることを考慮し、早めに対応することをおすすめします。
