兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺留分は、放棄することも認められています。 遺留分放棄の手続きは、被相続人の生前と死後で異なります。特に生前の遺留分放棄は、家庭裁判所によって厳しく審査される点に注意が必要です。 この記事では遺留分の放棄について、相続放棄との違い、被相続人の生前・死後における手続きや注意点などを解説します。


兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺留分権利者の方が相続できた遺産が少なすぎる場合は、他の相続人などに対する遺留分侵害額請求を検討しましょう。この記事では遺留分について、権利がある人・法定相続分との違い・計算方法などをわかりやすく解説します。


兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には「遺留分」が認められています。相続などによって取得した財産が遺留分額を下回った場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。遺留分額を計算するためには、遺留分割合を確認する必要があります。この記事では、遺留分の計算例やケース別シミュレーションを紹介します。

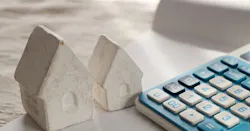
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められていますが、権利行使に当たっては消滅時効に注意が必要です。時効完成前に遺留分侵害額請求を行うため、早めに弁護士へ相談しましょう。この記事では遺留分侵害額請求権の時効について、期間・止める方法・過ぎたかもしれない場合の対処法などを解説します。


他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたら、請求が妥当かどうかを確認した上で対処方針を決めましょう。弁護士に相談すれば、遺留分侵害額請求への対応をサポートしてもらえます。この記事では遺留分侵害額請求を受けたケースについて、確認すべきポイントや対処法・注意点などを解説します。


推定相続人である子どもと仲が悪い場合は、その子どもに遺産を一切与えたくないと考えることもあるかと思います。ただし、子どもには遺留分が認められているため、遺産を一切与えないようにすることは原則としてできません。この記事では遺留分を渡さなくて済む5つのケースについて解説します。


兄弟姉妹以外の相続人には、相続などにより取得できる財産の最低ラインとして「遺留分」が認められています。現行民法では、遺留分を確保する方法は「遺留分侵害額請求」とされていますが、2019年6月以前に相続が発生した場合は「遺留分減殺請求」を行うことになります。弁護士に相談して、どのような方法で遺留分を確保すべきかを検討しましょう。この記事では遺留分減殺請求について、改正による変更点や手続き・期限・かかる費用などを解説します。


兄弟姉妹以外の相続人の方は、相続できた遺産が少なかった場合には、他の相続人などに対する遺留分侵害額請求を行いましょう。遺留分侵害額請求には期限があるので、早めに弁護士へ相談することが大切です。また、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合にも、弁護士への相談をおすすめします。この記事では遺留分侵害額請求について、請求方法・期限・請求された場合の対処法などを解説します。


被相続人の兄弟姉妹は相続人になることがありますが、遺留分は認められていません。 したがって、遺言書で相続分をゼロとされた兄弟姉妹は、遺産を相続できないのが原則です。それでも納得できない場合は、弁護士に相談して対応を検討しましょう。この記事では、兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由や、遺言書で相続分をゼロとされた兄弟姉妹が遺産を相続する方法などを解説します。

