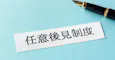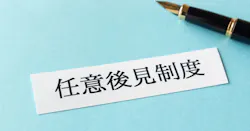「親の判断能力が落ちてきたけど、成年後見人だと権利を奪いすぎる気がする」 そんな方に検討してほしいのが、後見人よりも本人の判断の余地が残されている「保佐人(ほさにん)」という制度です。 保佐人とは、親の「自分で決める自由」を最大限に残しつつ、借金や不動産処分などの「大きなリスク」を防ぐことができる、後見人と補助人の中間に位置付けられる制度です。 本記事では、保佐人と後見人の違い、保佐人にできること(権限)、手続きの流れを、弁護士監修でやさしく解説します。 「自分の親にはどの制度が最適?」と迷っている方は、ぜひ参考としてお役立てください。

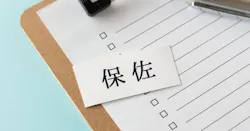
成年後見に関する登記事項証明書は、成年後見人が本人を代理して法律行為をする場合や、本人がした法律行為を取り消す場合などに必要です。 この記事では成年後見に関する登記事項証明書の請求方法や必要書類、有効期限などを解説します。


「補助人」とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人をサポートする人です。初期の認知症と診断された場合には、補助人の選任申立てを検討するとよいでしょう。 この記事では補助人について、できること・後見人や保佐人との違い・選任方法・報酬などを解説します。

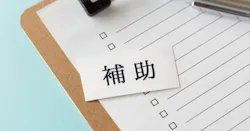
判断能力が低下した人のために成年後見人を選任してもらうには、家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行う必要があります。後見開始の申立ては自分でもできますが、難しければ弁護士などへご相談ください。 この記事では成年後見人の選任手続きについて、流れや必要書類などを解説します。


成年後見制度は、判断能力が低下した人を詐欺や浪費から守るための対策となります。 ただし、成年後見制度を利用する際には、一定の費用がかかることに注意が必要です。成年後見制度の費用・報酬はいつまで払うのか、報酬が払えない場合の対処法などを解説します。


任意後見制度を利用すると、認知症などに備えて、財産を管理してもらう人をあらかじめ指定できます。法定後見(成年後見・保佐・補助)との違いや、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解した上で、状況に合わせて使い分けましょう。この記事では任意後見制度について、メリットやデメリット、成年後見との違い、費用などを解説します。