

家族が亡くなった直後の時期には、以下の手続きを行う必要があります。短期間のうちに対応する必要があるため、早い段階から着手しましょう。期限別に紹介します。
医療機関で受け取ります。死亡届の提出時に添付が必要です。
以下のいずれかの市役所・区役所・町村役場に提出します。
・被相続人の死亡地
・被相続人の本籍地
・届出人の所在地
年金事務所または街の年金相談センターに提出します。 日本年金機構に被相続人の個人番号が収録されている場合は、原則として省略可能です。
年金事務所または街の年金相談センターに提出します。 日本年金機構に被相続人の個人番号が収録されている場合は、原則として省略可能です。
保険者(市区町村・国民健康保険組合など)の窓口に返却します。 職場の健康保険に加入している場合は、事業主の指示に従います。
保険者(市区町村)の窓口に提出します。
被相続人が世帯主の場合、被相続人の住所地の市役所・区役所・町村役場に提出します。
被相続人が死亡時に所有していた財産については、遺産相続の手続きを行う必要があります。対応すべき主な手続きは以下のとおりです。
期限 | 手続きの内容 |
|---|---|
早めに | 遺言書の有無の確認 |
相続の開始を知った時から3か月以内 | 相続放棄・限定承認 |
相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告 |
相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年以内 | 遺留分侵害額請求 |
相続の開始および不動産の所有権の取得を知った時から3年以内 | 不動産の相続登記 |
次の項目で、それぞれについて詳しく解説していきます。
家族が亡くなって相続が発生したら、亡くなった家族が所有していた遺産を分ける必要があります。そのための事前準備として、以下の作業を早めに行いましょう。
手続きの内容 | 方法 |
|---|---|
遺言書の有無の確認 | 被相続人の遺品等を探す。公証役場や遺言書保管所(法務局・地方法務局)に保管されていないかどうかも確認する |
相続人の調査 | 市区町村役場から取得できる戸籍謄本類を確認して調査する |
相続財産の調査 | 財産・債務の種類によって異なる |
上記の作業が完了したら、遺言書によって相続する人が指定されていない遺産について、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議には、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合います。
合意ができたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、各相続人が印鑑登録された実印を押すことが必要です。
遺言書または遺産分割協議によって遺産分割の内容が確定したら、その内容に従って遺産の名義変更を行いましょう。
たとえば、預貯金や有価証券については金融機関に相続手続きを申請します。自動車については、運輸支局で登録名義の変更を行います(不動産の相続登記については後述します)。
これらの手続きに期限はありませんが、期限のある他の相続手続きの前提となるものが多いので、早めに対応することをおすすめします。
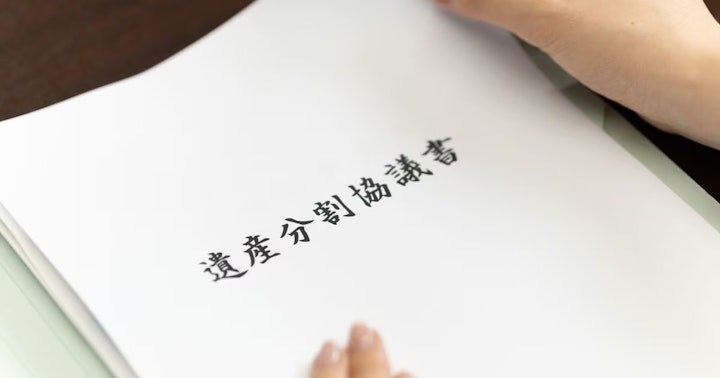
被相続人が借金を負っていた場合には、相続放棄または限定承認を検討しましょう。 相続放棄は債務を含む遺産を一切相続しない意思表示(民法939条)、限定承認は資産を相続しつつ、債務は資産の限度でのみ相続する意思表示です(民法922条)。いずれも、マイナスの財産を相続する事態を回避できます。
相続放棄と限定承認は原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
相続放棄または限定承認をすべきかどうかを適切に判断するためには、相続財産の調査が不可欠です。短期間のうちに対応する必要があるので、早めに検討を始めましょう。
相続放棄の手続きについては、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:相続放棄の必要書類を子、兄弟など続柄別に解説 戸籍謄本の取得方法も紹介

被相続人が亡くなった年の所得については、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。 所得税の準確定申告は、通常の確定申告と同様に、納税地の税務署に対して申告書を提出して行います。必要に応じて税理士などのサポートを受けながら、早めに準備を進めましょう。
相続財産等の額が基礎控除額を上回っている場合や、小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合には、相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告期限は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了しない場合は、暫定的に法定相続分に従って申告を行い、後に更正の請求または修正申告によって税額を修正することになりますが、二度手間になってしまいます。
二度手間を回避するため、相続税の申告期限までに遺産分割を完了することが望ましいです。
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています(民法1042条1項)。
遺留分は、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。取得した財産の額が遺留分に満たない場合は、他の相続人などに対する遺留分侵害額請求によって、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効により消滅します。時効が完成する前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行いましょう。
具体的な請求のやり方については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?請求のやり方や期限、請求された場合の対処法も解説
相続・遺贈によって取得した不動産の所有権を第三者に対抗するためには、相続登記(所有権移転登記)の手続きを行わなければなりません(民法177条)。
2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、相続の開始および相続・遺贈による不動産の所有権の取得を知った時から3年以内の相続登記が義務化されます。
改正法の施行前に相続・遺贈による不動産の所有権の取得を知った場合にも、2027年4月1日までに相続登記の手続きを行うことが必要です。

相続手続きの期限を過ぎると、以下のような不利益が生じるおそれがあります。トラブルを避けるため、期限を守って計画的に相続手続きを進めましょう。
相続手続きの種類 | 期限を過ぎた場合の不利益 |
|---|---|
相続放棄 | 法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなる(民法921条2号) |
所得税の準確定申告 | 税務調査を経た後、本税に加えて延滞税および無申告加算税または重加算税が課される |
相続税の申告 | 税務調査を経た後、本税に加えて延滞税および無申告加算税または重加算税が課される |
遺留分侵害額請求 | 遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成し、遺留分を確保できなくなる(民法1048条) |
不動産の相続登記 | 10万円以下の過料に処される(改正不動産登記法76条の2第1項、第2項、164条)。 |
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対処法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:相続放棄できる期間は3か月!期限を延長する方法はある?期限を過ぎてしまった場合の対処法も解説
遺産相続の手続きは多岐にわたりますが、期限がある手続きも多く、計画性をもってスムーズに対応しなければなりません。自力で対応することが難しい場合には、弁護士に相談しましょう。
弁護士には、さまざまな相続手続きの代行を依頼できます。また、遺産分割の方法について相続人同士で揉めている場合には、その調整を弁護士に依頼することも可能です。
相続手続きに関するお悩みは、弁護士にご相談ください。
