
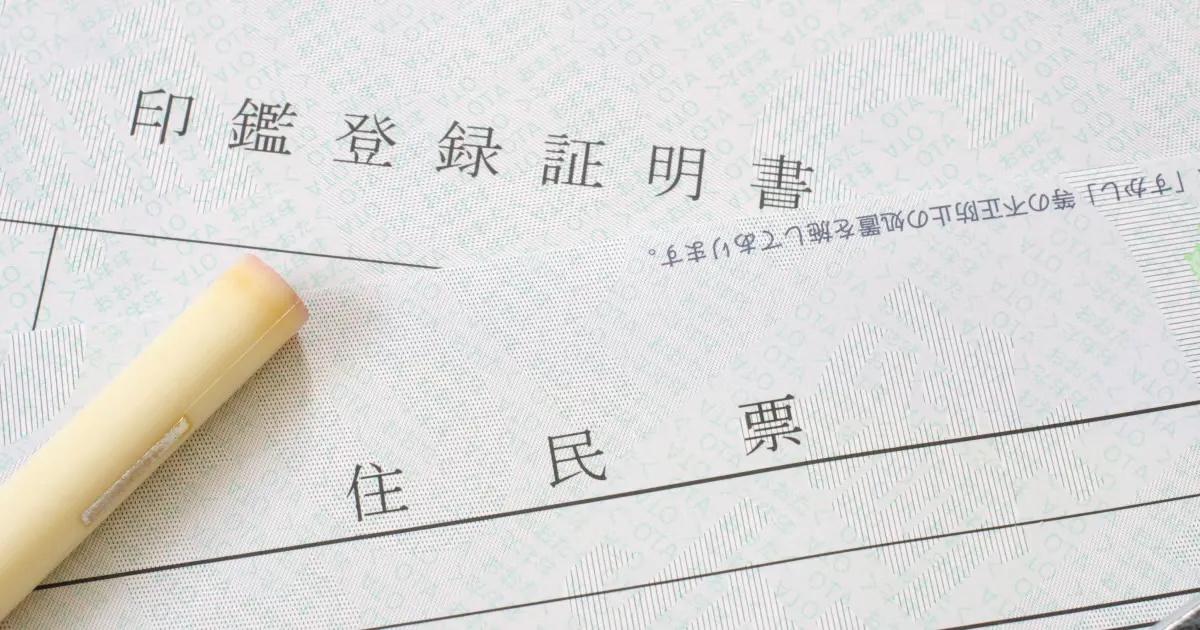
相続放棄を行うには、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を担当する家庭裁判所で手続きします。その際、決められた書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
必要書類には、どの相続人が相続放棄をする場合でも共通して必要な書類と、相続放棄をする相続人の属性によって必要となる書類があります。
どの相続人が相続放棄をする場合でも必要な書類は、以下のとおりです。
相続放棄の申述書は、相続放棄をする相続人が20歳以上の場合と20歳未満の場合とで書式が異なります。
相続放棄をする相続人が20歳以上の場合の申述書は、こちらからダウンロードできます。
相続放棄をする相続人が20歳未満の場合の申述書は、こちらからダウンロードできます。
郵便切手は、家庭裁判所によって必要な額が異なるので、家庭裁判所に確認しましょう。
相続放棄をする相続人の属性によって、それぞれ以下の書類が必要になります。
被相続人が死亡した時点で、本来の相続人(子・親・兄妹など)が死亡していたり、相続する権利を失っていたりしたなどの場合、「本来の相続人」の代わりに、孫や祖父母、甥・姪が相続します。「代襲相続」というルールです。
本来の相続人が子の場合で、孫も死亡していた場合には、「ひ孫→玄孫」というように、下の世代が相続していくことになります。本来の相続人が親で、祖父母も死亡していた場合には、曽祖父母というように、上の世代が相続していきます。本来の相続人が兄弟姉妹で、甥姪も死亡していた場合には、その子どもたちには代襲相続されません。
相続放棄の手続きは、相続開始から3か月以内に行なう必要があります。この期限に間に合わない場合には、期限を延長(伸長)するための手続きをすることができます。
相続放棄の期限を延長するために必要な書類は、どの相続人が相続放棄をする場合でも共通して必要な書類と、相続放棄をする相続人の属性によって必要となる書類があります。
どの相続人が相続放棄の期間の延長を申し立てる場合でも必要な書類は、以下のとおりです。
郵便切手は、家庭裁判所によって必要な額が異なるので、家庭裁判所に確認しましょう。
相続放棄の期限を延長をする相続人の属性によっては、上記の共通して必要な書類に加えて、別の書類も提出します。相続人の属性によって求められる必要書類は、相続放棄をする際に相続人の属性によって求められる必要書類と同様です。
兄弟全員で相続放棄をする場合、1人が他の兄弟の分もまとめて手続きをすることができます。
その際、相続放棄の申述書は、兄弟それぞれが作成したものを提出する必要があります。
一方、同じ内容の書類は、1通あればよいということになっています。たとえば、「被相続人の住民票の除票または戸籍の附票」「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」などは1通で足ります。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄する場合の費用や必要書類については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:相続放棄を兄弟姉妹でまとめてする方法、必要書類や費用を解説
相続放棄に印鑑証明は必要ありません。
もし、他の相続人などから相続放棄の必要書類として印鑑証明を求められた場合、法的な意味での相続放棄ではなく、相続財産をあなた以外の相続人で分け合う(あなたの取り分を0にする)という内容の遺産分割協議である可能性があります。
なぜ印鑑証明が必要なのか、理由をよく確認した方がよいでしょう。
家庭裁判所によっては、それぞれのホームページで相続放棄の必要書類を公開しているので、紹介します。
この一覧にない家庭裁判所の多くは、全国共通の書式を使用しています。念のため、申請先の家庭裁判所に必要書類を確認すると確実でしょう。
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、必要書類の収集や申述書の作成が手間だと感じる場合、弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。3か月という限られた期間内にすべての手続きが完了するよう、迅速に対応してもらうことができます。
弁護士に依頼することで、そもそも相続放棄をすることが適切かどうかも判断してもらえるでしょう。相続放棄すべきかどうか迷っている場合は、弁護士にアドバイスを求めることも1つの方法です。
