※利用規約・個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
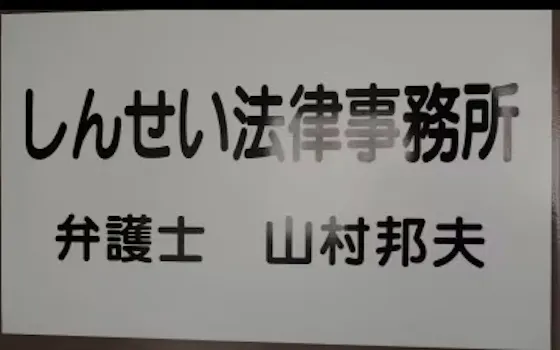


| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町1203 |
| 最寄駅 | JR仙台駅、JR仙石線あおば通り駅、仙台市地下鉄広瀬通駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜21:00 / 日曜 9:00〜21:00 / 祝日 9:00〜21:00 |
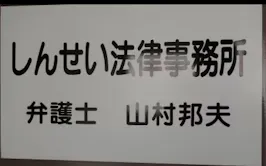


クリックすると大きく表示されます。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町1203 |
| 最寄駅 | JR仙台駅、JR仙石線あおば通り駅、仙台市地下鉄広瀬通駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜21:00 / 日曜 9:00〜21:00 / 祝日 9:00〜21:00 |
【弁護士歴30年以上】相続問題でお困りの方へ、仙台のしんせい法律事務所がトータルサポート◎法定相続分を基に、合理的かつ納得のいく解決を目指します◆休日・当日相談可能◆まずはお気軽にお問い合わせください《Webで簡単予約》
弁護士として約30年、ここ仙台の地で様々なご相談をお受けしてまいりました。長年の経験で培われた一番の強みは、ご相談いただいた時点から、その問題が最終的にどのような結論になりそうかという「見通し」を的確に立てられることです。
そして、一つの方法に固執するのではなく、ご依頼者さまにとって最善の結果となるよう、解決方法の選択肢を数多くご提案できることだと自負しております。
どうぞ安心してご相談ください。
ご依頼者さまのご希望をうかがった際、法律的にその実現が難しいと予測されるケースもございます。
しかし、私は「無理です」の一言で終わらせることはいたしません。ご希望がそのまま通らないとしても、それに代わるどのような解決策があるのか、ご意向に少しでも近づける方法はないか、あらゆる選択肢を検討し、ご提案することこそが弁護士の役割だと考えています。
最後まで諦めずに、ご依頼者さまと一緒に解決への道筋を探し続けます。
ご家族間の相続問題では、長年の不平不満が噴出し、感情的な対立に発展しがちです。しかし、弁護士の役割は、ご依頼者さまと一緒になって感情論をぶつけることではなく、冷静に法的な主張を行い、最終的に数字として遺産をどう分けるかという着地点を見出すことです。
もちろん、介護のご苦労といったお気持ちが「寄与分」として法的に評価されるのであれば、その点はしっかりと主張します。あくまでご依頼者さまのお考えを尊重し、最終的な方針決定をサポートします。
「一部の相続人に有利な遺言は、無理やり書かせたものではないか」「親の面倒を見てきた兄弟が遺産を独り占めしようとしている」といった、根深い不信感が絡むご相談にも数多く対応してきました。
遺言の有効性を争うために、当時の医療記録を取り寄せて状況を調査したり、弁護士照会で金融機関の取引履歴を調べ、財産の全体像を明らかにします。
ご依頼者さまの正当な権利である「寄与分」や「遺留分」の主張もしっかりと行います。
相続手続きは、遺産分割だけでなく、相続税の申告や不動産の名義変更など、弁護士以外の専門家の協力が必要な場面が少なくありません。
当事務所では、弁護士としての30年の経験から、ご相談内容に応じて、税理士や司法書士といった他の専門家のサポートがいつ必要になるかを的確に判断し、次に進むべき道筋をアドバイスいたします。
ご依頼者さまが手続きの途中で迷うことがないよう、しっかりと道案内をさせていただきます。
本気で問題を解決したいとお考えの方のために、初回のご面談は弁護士ドットコムをご覧になった方限定で30分無料としております。
お電話でのご相談は行っておりませんので、まずはウェブサイトのフォームからご希望の日時などをお知らせください。
ご依頼者さまの状況に合わせ、柔軟な体制でお待ちしております。
相続問題は、お医者さんへの相談と同じで、早めの対処が何よりも重要です。特に遺留分の請求には1年という短い期限があります。
相談が遅れたことで、本来主張できたはずの権利を失ってしまうといった不利益を避けるためにも、まずは一度、専門家の話を聞いてみませんか。ご依頼いただくかどうかは、その後にゆっくりお考えいただければ結構です。
仙台の事務所で、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。
初回相談料 | 5,000円/30分まで |
|---|
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町1203 |
| 最寄駅 | JR仙台駅、JR仙石線あおば通り駅、仙台市地下鉄広瀬通駅 |

【仙台市で地域密着】相続問題の相談実績多数◆遺産分割/遺言作成/相続放棄など幅広く対応◎30年以上の経験と、提携士業との連携でスムーズな解決を目指します。まずはお気軽にご相談ください!【事前予約で夜間土日対応可能】

【遺産分割・遺留分に注力】【東北各地より相談・解決実績多数】【有名雑誌に掲載多数】【初回相談60分無料】遺産分割や遺留分の問題を迅速に解決◎依頼者の想いを大切にし、親身に寄り添う対応を心掛けています◆土曜も営業、クレジットカード払い対応◆相続の悩みはお早めにご相談を

【初回相談無料|仙台で30年の実績】遺産分割/遺言書作成など、相続トラブルを円満解決へ◆経験豊富な弁護士が親身にサポート◎他士業との連携でワンストップ対応!《土日祝・夜間相談可》まずはお気軽にご相談ください。